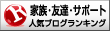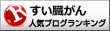目次(Contents)
順調すぎる回復
前回のブログ 手術後の父
『もしかしたら、このまま退院できないリスクがないわけではないです』
と手術直後に主治医の先生がおっしゃった最悪のケースからはかけ離れて、順調に回復していった父。
回復している姿を見るのは嬉しいけれども、このN大病院は、それなりに元気になったら退院する必要がある大病院。けれども、手術後はストーマ(人口肛門)のサイズが安定して、その取替えを自分でスムーズに出来るようならないと退院は出来ませんと言われていました。
慣れないはずのストーマの処理を看護師さんから教わりながら、時には文句を言っていたものの、思った以上に父は順調に回復をしていました。
そして、看護師さんやヘルパーさんたちが、「うちの食事はあまり美味しくなくて…( ;∀;)」と申し訳なさそうにおっしゃっていた食事もいつも完食していました。
医療連携センターからの連絡
私が父の退院を強く希望したことは主治医から大学病院に設置されている医療連携センターの担当看護師さんに手術後早々に伝えられたそうです(後からそういう仕組みがあることを知った私)。
ということで、病棟の看護師さんから案内を貰って医療連携センターの担当看護師さんとお話をすると幾つかの提案を受け取りました。
① 父の場合は末期癌(ステージⅣ)で高齢でもあるので、早めに介護認定の手続きに入った方が良いので、私が住んでいるA市M町の地域包括支援センター(すでにサイトのコピーを用意してくれていました)に早めに連絡を取ること。
地域包括支援センターについては以下のサイトが分かり易いです。
地域包括支援センターとは?
② 人口肛門を付けたので、障碍者認定を受けるとストーマに掛かる費用の一部負担を受けることが出来るため、早めに市役所の障碍者福祉課に行って認定手続きについて相談を受けること。
人口肛門を付けた時に必要なストーマについては以下のサイトが参考になります。
ストーマについて
③ 父が自宅で自立して生活が出来るように訪問看護師さんを医療連携センターで見つけるので、見つかったら在宅医療の方法を考えること。
幸い、私は元公務員でもあり、公認会計士でもあるので、畑が違ってもこういう手続きの類は慣れているため、後はネットで調べて一つ一つ対応していったのですが、とにかくかなり面倒な手続きでした。多くの人にとって、これらの手続きを効率のよい順番でこなすのはなかなか難しいそうです。
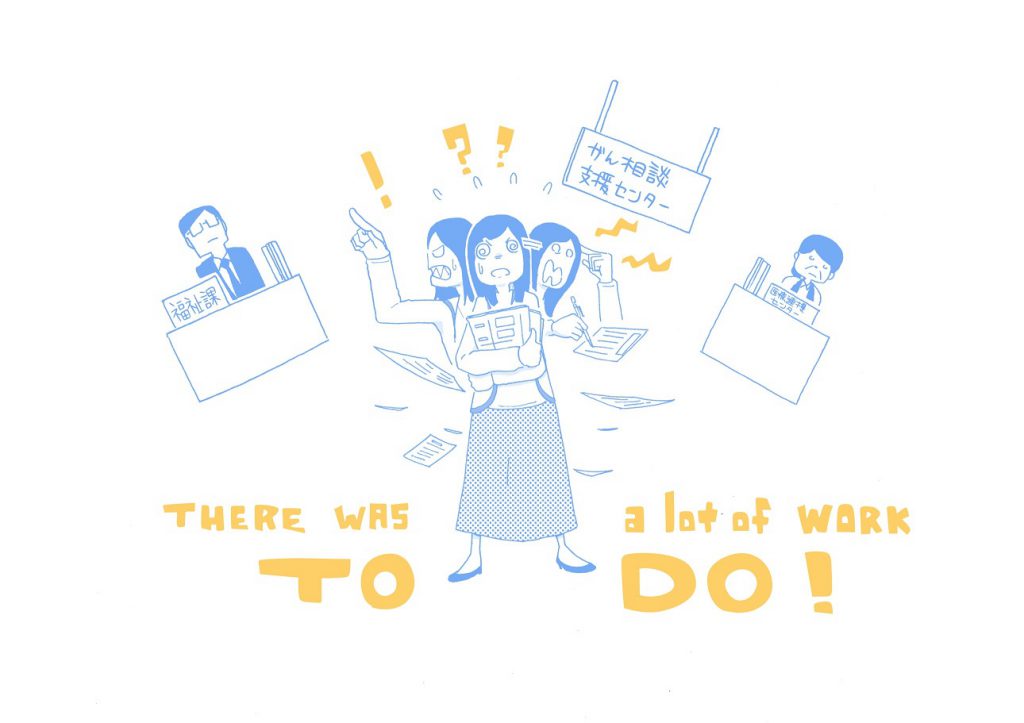
また、経済的に苦しい人や、自分や家族だけで判断できなくて困っている人、身寄りがない人などいろいろな事情を抱えている患者さんも沢山います。そのような患者さんのために、病院には、「医療福祉相談センター」や「がん相談支援センター」なども併設されています。
午後に病院に行くと、これらの施設はいつも混み合っていました。
少なくとも私と父は経済的に困ることはないわけですが、どんなに家族が一生懸命でも、やはり金銭的に余裕がない家族の方たちは深刻そうな雰囲気で相談に来ていらっしゃいました。
『自分で対応出来るだろう』
と判断をした私は、このような施設は、出来るだけ困っている人に譲るべきだと判断をしました。
幸いに、父は自身が末期癌であることは理解はしていても、性格が変わったり自暴自棄になったりしていなかったことは幸運だったと思います。
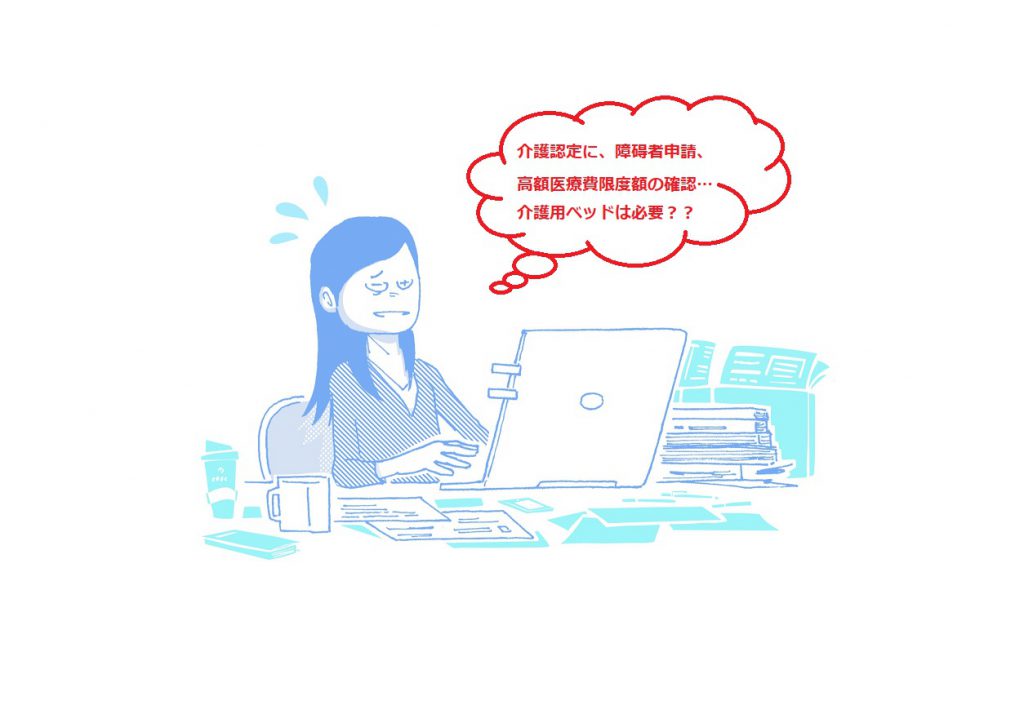
入院中のお金の管理
お金に困るわけではありませんでしたが、父が順調に回復をしていたこともあり、色々な手続きが一気に押し寄せて、また、人口肛門に必要なストーマは決して安くなく、病院と自宅の往復の交通費、各種手続きのために必要な診断書を取るための費用など、最初に困惑をしたことは、『どのような費用が掛かることが想定されていて、それがどれくらいの金額になるのか、そして毎月継続して掛かる費用が何で、スポットで掛かる費用が何なのか?』
が全く見えない中で同時進行で色々な手続きをしていたため、そもそも幾らくらいお金が必要なのか(1か月単位で)この入院で全く見当がつかなかったことは、とても困惑しました。
資金的余裕がないわけではなく、また、父の場合は末期癌で決して長くない期間であることは分かっていても、やはり、幾らくらいかかってそれはどのようなものなのか?予め分かっていればどれだけ安心できたか?振り返ると切実に思います。
ということで、次回のブログでは、父の1回目の入院にかかった費用や必要な手続きなどを整理して、このブログを読んでくださっている方の参考になればと思っています。
To be continued
(ブログランキングに参加しています!)